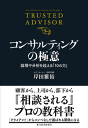マーケティングアイズ、法人化4周年記念イベント のテーマ「顧客中心主義 Customer Cerntric」
ビジネスライブの第3部で話す内容は、
- 行動観察
- ビッグデータ
- 市場を知る4つの方法
- ビジネス版「ジョハリの窓」
などを、ハーバード・ビジネス・レビュー2014年4月号の記事を参考に、



(*アマゾンではこちら↑)
また、
- 顧客価値
- 顧客体験 とその最大化
- 顧客ポートフォリオと戦略
を、バトル先生の「Customer Relationship Management~Concept & Technology」
を参考に、こちらは大学院での講義での引用を話します。



(*アマゾンではこちら↑)
興味のある方はぜひまず先に読んでみてください。かなり参考になる事柄ばかりです。
今回も、もちろん学術的なことではなく、
セオリーやフレームワークを、分かりやすく具体的に、
中小企業や個人事業主が「どう活用すればいいのか」をお話しします。
ご参加の皆様、今から楽しみにしています。
マーケティング コンサルタント
理央 周
このブログの定期購読はこちらから ⇩

新規事業・ビジネスモデル開発を目指す経営者の方はこちら:→マーケティング アイズ
売れる理由を学ぶメルマガ⇒ 「なぜか売れる」の公式バックヤード」 では、ヒット商品に共通する「仕掛け」はマーケティングにあり!という記事を毎週発刊していきます。詳細はこちらから:

関連記事はこちらです:↓
学研パブリッシングさんのMook「仕事の教科書~絶対にミスをしない人のSPEED仕事術」の中の、
「できる人の時短テク」という特集で掲載をしていただきました。

ボクは、その特集の中で、
「デスクが狭くて仕事がはかどりません」
「マルチタスクを処理しきれません」
「仕事と関係ないことに時間を取られてしまいます」
「仕事の優先順位づけにこまっています」
「急に入る仕事に追われています」
という問いに答えています。

元来気が短いので、このようなことを毎日考えている結果、
「サボる時間術」など、2冊の時間術の本を書くことにつながったのかな、
と思います。




ドラッカーも言っている通り、時間は重要ですが、
スケジュールを先に管理してはいけません。
やはり、タスク、つまりやるべきことを先に整理整頓し、
成果につながる仕事をするにはどうしたらよいか、をまずは考えるべきです。
そして、時間軸を考え、しっかりと時系列で片づけていくべきです。
時間は有限で必要不可欠だし、なにより代替不可能です。
重要な経営資源として認識することが必要です。
これで、年内に出版する久しぶりの時間術の本が、ますます楽しみです!
ご紹介いただきましたこの本のスーパーバイザー、株式会社戦国 総大将の 美崎栄一郎さん、
ありがとうございました!
マーケティング コンサルタント
理央 周
このブログの定期購読はこちらから ⇩

新規事業・ビジネスモデル開発を目指す経営者の方はこちら:→マーケティング アイズ
売れる理由を学ぶメルマガ⇒ 「なぜか売れる」の公式バックヤード」 では、ヒット商品に共通する「仕掛け」はマーケティングにあり!という記事を毎週発刊していきます。詳細はこちらから:

関連記事はこちらです:↓
ウェブとはすなわち現実世界の未来図である 読了

この本を読み、ネットのオープン性についての「気づき」をもらい、また再びオープン性について考えるいい機会にもなった。
第2章「シェアが生み出す新しい資本主義」では、参加者が何者であるか、が問われるとある。
それは、実名で投稿・コメントせよ、という意味でなく、
提供する側にもされる側にも継続的に「信用が担保されているかどうか」が重要になる、
ということ。
新しい資本主義、というのはITの発達でSNSが普及し、
これまで、リアル店舗やホームページでしかできなかったモノやサービスの販売、
あるいはイベントへの集客が「SNS」を通してできるようになったこと、
また、情報を共有する(=シェア)ことが、その商取引をよりスムーズにしていることだと言える。
中小企業や個人事業主が、フェイスブックやインスタグラムを活用する場合に当てはめてみる。
「何者であるかが問われる」ということは、
シェアすることによる商取引上において、単に「売る」「稼ぐ」「儲ければいい」ということや、それらの行為を「あおる」ことがより簡単になった。
しかしビジネスと経営には「永続的な成長」が必要である。
誰でもシェアできる、ということは
「誰が何をやってもいい」
ということではない。
SNSやITはいちメディアでしかなく、活用したとしてもに人間が本来持つべき、
誠意や顧客への想いを無くしては「もともこ」もない。
継続するには、
- 自社・自身が「何」を提供し、
- 提供物が顧客に「何を」もたらすかを、
明確にせよ、
と著者は語っていると解釈した。
第3章にある、顧客の声を可視化するプログラムとして、「マイスターバックス」と、Dellの「アイディアストーム」を上げている点も面白い。
ひいては、日本企業が欧米企業のこのようなオープン化ができない要因の一つに、
不要で行き過ぎたインターナル・マーケティング=上司説得型マーケティングを上げている点も興味深い。
企業の規模が大きくなるにつれて出てくる、いわば大企業病だ。
ウェブの進化によるオープン化が進むんだとしても、必ずしもいいことばかりは発生しない。
このような反ポジティブな現象も起きてくる。
ウェブが一般的になり始め、まずは礼賛され、今は氾濫しすぎて「おいおい、大丈夫か」という風潮も多分に見られる。
ボクもそうなのだが、著者は私たち人間がウェブを活用し、
「ポジティブ」な未来を造ることができる、と言っているように読める。
この点、共感できるし、読み心地がいい。
ウェブ礼賛の第2フェイズにこれからなる中でも、読んでおくべき一冊だと思われる。


マーケティング コンサルタント
理央 周
このブログの定期購読はこちらから ⇩

新規事業・ビジネスモデル開発を目指す経営者の方はこちら:→マーケティング アイズ
売れる理由を学ぶメルマガ⇒ 「なぜか売れる」の公式バックヤード」 では、ヒット商品に共通する「仕掛け」はマーケティングにあり!という記事を毎週発刊していきます。詳細はこちらから:

【顧客中心主義】~マーケティング白熱ライブ2015 マーケティングアイズ4周年記念イベント


関連記事はこちらです:↓
「世界に冠たる中小企業」読了。

ボク自身、中小企業での勤務経験もあるし、また今も中小企業や個人事業主の経営相談をさせていただいていることもあり、手に取ってみた。
世界に通用する、とくにモノ作りの企業が日本には多い。
一方で、価格競争や外資系企業の流入などで苦戦している企業が多いのも事実である。
そんな中で、中小企業が活路を見出すにはどうすればいいのか?
ボク自身の永遠の課題でもあるのだが、そのヒントが多く書かれている。
この本の著者は、ジャーナリストということもあり、各企業の実情が正確に取材され克明に描かれている。通常のビジネス書は、経営関係の人たち、例えばコンサルタントや士業の方々、学者の先生が書いているため、読み手の再現性も考えてまとめられていることが多い。著者はこういったプロフェッショナルよりも、さすがはジャーナリスト、という感じで写実的に書いている。その分だけ、読み手は自分で解釈をしなければならない。そこが面白いとも言えるのだが。
ボクが特に感銘したのは、価格競争に巻き込まれないための大きなヒントになる、
第2章「専門分野に特化」が成功のカギ に書かれている、東海バネ工業の事例。
「大量生産はしません。100個200個の注文でも他社にお願いします」と言うという。
そのラインアップは、日常生活用途のものからはやぶさまでとのこと。
もちろん値引きはせず、2014年度の売上は約19億円、粗利約50%、営業利益12%。素晴らしい数字である。そのヒミツは多くあると思われる。
- 正当な利益の見込める価格でしか受注しない
- 完納率99.9%〜仕組みとして過去の受注経歴の情報がすべての部署で共有されている
- 在庫をできる限り多く持つ
という点にある。
1に関して言えば、値引き合戦に巻き込まれずまたブランド価値を守れる。
2については、顧客の信頼に直結する。
3に関しては、一般に考えられていること、たとえばROA(総資産利益率)を重視するような傾向とは逆の発想になる。
特に2と3に関しては「顧客」のことを常に考えているのでできる発想である。
逆にいうと、自社のことを最優先していたらでてこない発想ということになる。
しかし、東海バネのやり方をそのまま真似してもうまくいかない。
自社の状況を正しく把握し、あてはめていく、というステップになる。
そのために必要な第一歩は「売り手目線」を「買い手目線」に転換することであろう。
このような事例が数多く書かれているので、中小企業経営者はもとより、私のようなコンサルタントにとって,非常に有益な一冊である。


マーケティング コンサルタント
理央 周
このブログの定期購読はこちらから ⇩

新規事業・ビジネスモデル開発を目指す経営者の方はこちら:→マーケティング アイズ
売れる理由を学ぶメルマガ⇒ 「なぜか売れる」の公式バックヤード」 では、ヒット商品に共通する「仕掛け」はマーケティングにあり!という記事を毎週発刊していきます。詳細はこちらから:
 【顧客中心主義】~マーケティング白熱ライブ2015 マーケティングアイズ4周年記念イベント
【顧客中心主義】~マーケティング白熱ライブ2015 マーケティングアイズ4周年記念イベント

関連記事はこちらです:↓
「コンサルティングの極意」を読んでみた。

帯に書いてあるのが、
顧客、上司、部下から「相談されるプロの教科書」
とあり、さらに「クライアントからコンペ無し手で選ばれる関係になる」とあるのも、
自社、また自分をマーケティングしていくことで、営業努力や価格訴求とは別な次元で選ばれるようにする、という内容である。
それを実現するために「10の力」として書いている。
最初の3章の読み方〜コンサルタントとしての基礎
最初の3つの、「聞く力」「献身力」「先見力」は、他でもよくいわれていることに一見見えてしまう。しかし、その内容は私のようなフリーランスのコンサルタントが持つべき「心構え」をして、重みがあり再現性が高い。
例えば、「依頼人」として理解されている「クライアント」をローマ帝国の例をあげて、
「後援者」と呼ぶ方がふさわしい、と言っている。
依頼人だと定義した瞬間に、仕事を出す人・受ける人、という関係にしかならなくなってしまうため、私自身も違和感を覚えていたのだが、これですっと腑に落ちたのだ。
これらの話しに普遍性と再現性がともにある理由は、著者がコンサルタントになる前に、
パルコという事業会社で働いた経験が、コンサルティングとクライアントサイドとが、
双方で何が必要な要件なのかを理解されているからなのだろうと推測できる。
4章以降の読み方〜コンサルタント力の応用編
4章目以降には、著者の経験がますます反映された内容が色濃くでてくる。
私にとって、第4章からはコンサルタントとしての応用編、という感覚で読み、そのまま使える知識になった。
第5章の「巻き込み力」で、コンサルタントの仕事の目的を「人を動かすこと」と定義している。
まさに、その通りでクライアントが動き初めて成果につながるのである。
したがって、「紙に書いた言葉だけでは人は動かない」とあるこの章には、コンサルタントとしてどう動けばよいか、必要な人たちとコミュニケ―ションをとり、そしてクライアントをいかに動かすか、のヒントが多く書かれている。
共創力の章では、コンサルタントから提案だけで済んでいたのは20年前まで、
今はクライアントとともに創り出すのだ、とある。
そして、コンサルタントは洗濯をする時に泡を立たせる洗濯板で、
尖がったしかし必要な情報を提供することでクライアントに驚きを与えねばならないこと。
好奇心を持つことで、知識を陳腐化させないこと
学び方そのものを学ぶべきということ
ロジカルシンキングだけでは足りなく、クリエイティビティと同時に保有すべきこと
ブランド構築は「時の結晶」であり、分かる人にだけ分かってもらえばいい、ということ
などなど、コンサルタントのあるべき姿が、実際の体験に基づいた形で説明されている。
しかし、単なる一個人の成功哲学に終わっているわけでないのは、
フレームワークや、多国籍企業との仕事によって培われた、
普遍的な事実が含まれているからなのだと感じる。
したがって、広く顧客から相談される人、つまりコンサルタントとしてのみでなく、
この本に何度も出てきたように、「プロフェッショナル」として必要な考え方と行動の仕方の、
多くのヒントを読み取ることができる。
さらにいえば、コンサルタントとして「どう稼ぐか」というよくあるような本に書かれているスキルよりも、もっと重要で不可欠なことが書かれている。これを活かせるかどうかは読み手の問題なのだ。
まさにその意味においては、コンサルタントのみでなく、
営業担当者や、中小企業経営者、個人事業主が読み実践することで、成果につなげられる1冊である。
マーケティング コンサルタント
理央 周
*こちらです↓ 右の2冊の本もおススメ。






新規事業・ビジネスモデル開発を目指す経営者の方はこちら:→マーケティング アイズ
理央 周 最新刊 ⇩


売れる理由を学ぶメルマガ⇒ 「なぜか売れる」の公式バックヤード」 では、ヒット商品に共通する「仕掛け」はマーケティングにあり!という記事を毎週発刊していきます。詳細はこちらから:⇩
 関連記事はこちらです:↓
関連記事はこちらです:↓



![Marketing i's [マーケティングアイズ]](https://www.businessjin.com/images/common/header_logo.png)

![Marketing i's [マーケティングアイズ]](/images/common/header_logo.png)